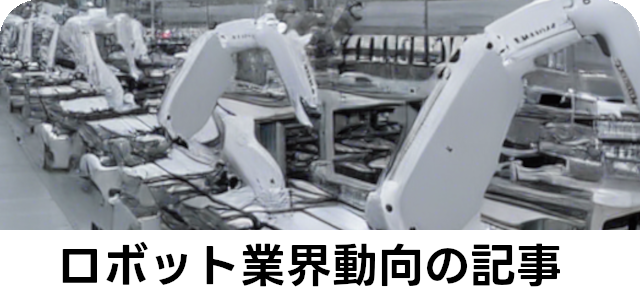協働ロボット
本記事はちょっとマニアックな小ネタです。 人とロボットが協働運転する際の要件事項のうちの「動力と力の制限」についてです。 「動力」と「力」という言葉が使い分けられている カギは2006年版にあり まとめのようなもの 「動力」と「力」という言葉が使い…
ときおり、「80W以下のロボットなら安全柵は不要なんでしょう?」という声を聞くことがあります。また、「協働ロボット=モータ出力が80W以下のロボット」と思っている方もいるかもしれません。 いわゆる「80W規制」については、法律と通達が絡んで混乱しが…
本記事は、制御(電気・ソフト)のことはあまり分からないという人*1が、大枠のイメージを掴むことを目的としています。設備に関して話をしていると、以下のようなワードが出てくると思います。 安全関連部 安全適合 カテゴリ3PLd ・・・ そのような用語が…
前記事の①は、長い前置きになってしまいました。 いよいよ本題の「安全適合の監視停止」について説明していきます。 fa-robot-watch.com 規格上は 世間の協働ロボットはカテゴリ2停止が多い 実際のシステムはどうなるか 単純な例 中間領域を設ける例 人とロ…
協働ロボットの要件の1つである「安全適合監視停止」について解説していきたいのですが、まずはロボットの「停止」について説明をしていきます。 主な出典は、ISO10218-1:2011(JIS B 8433-1:2015)、IEC60204-1:2016(JIS B 9960-1:2019)です。この辺は知って…
協働運転要求事項の1つである、「速度及び間隔の監視」*1について解説していきます。 なお、分かりやすさ優先で書いていきますので、詳細は規格を参照してください。 規格での記載 まずは間違った例から 正解はこちら 今後の展望 規格での記載 ISO10218-1(J…
協働ロボットのハンドガイドとダイレクトティーチの呼称について、整理してみたいと思います。 私は最初、ハンドガイドとダイレクトティーチは違うもの?と勘違いしていました。 先にまとめ 規格を確認 ハンドガイド ISO10218-1(JIS B 8433-1) TS15066(TS B …
前回の記事はほぼ規格の説明になってしまいましたが、後半の今回は実際の測定について紹介していきます。 ①を未読の方は、まずはこちらからどうぞ。 fa-robot-watch.com 測定装置の概要 力センサー・圧力センサー ばね おもり スライド機構 その他 測定方法 …
協働運転のシステム構築で、ロボットの接触検知機能*1を活用する場合、リスクアセスメントの一環として接触した時の人体へのダメージを評価する必要があります。 「どんな手順でどんな項目を実施するのだろう?」「まさか実際に人がぶつかってみるわけにもい…
昨日今日の話ではないのですが、協働ロボットのスペック上の最高速度がどんどん速くなっている事情と注意点について書きたいと思います。 ロボットの最高速度について 協働ロボットの速度記載方法 協働ロボットで手先速度を記載する理由 以前までの協働運転…
過去記事で「協働ロボットを一言で言うのは難しい」と書きましたが、そのことについて掘り下げました。 fa-robot-watch.com はじめに 狭義の"協働ロボット" 広義の"協働ロボット" 改めて「"協働ロボット"は一言でくくれない」 はじめに 産業用ロボットはJIS…
以前の記事で書いたように、Universal Robots社のUR+の登場を受け、各社がロボットを中心とした周辺機器・ソフトのエコシステムを構築しようとしています。 fa-robot-watch.com以下では、UR+も含め、各社のエコシステム構築状況について調べてみようと思いま…
Universal Robot社が展開する、「UR+」がロボット業界に与えた衝撃について書いていきたいと思います。 前置き プラグ・アンド・プレイとは ロボット業界のプラグ・アンド・プレイ 【本題】UR+のなにがすごいか 歴史は繰り返す Universal Robot社の思想 終わ…
最近脚光を浴びている協働ロボットですが、今後この勢いで盛り上がり続けるか、逆にしぼんでいくのか、考えてみました。 双腕ロボットが流行った時期があった ハイプサイクルに当てはめて考えてみる 双腕ロボットはどうだったか 協働ロボットはどうか 国際規…
「協働ロボットだから柵をつけなくてもいいんでしょ?」というのはよく聞くフレーズです。 が、ここにはいくつかの誤解が含まれていますので、解説していきたいと思います。 ※本記事は、私の私見も入っていますのでご了承ください。 誤解1・産業用ロボット…
協働ロボットは柵が要らないロボット、となんとなく思っている方も多いと思います。 では人とロボットの「協働」とはいったいどんな状態を意味するのでしょうか? その疑問に答えるような論文がありましたので、紹介したいと思います。 ベースにした論文につ…
産業用ロボットの動作範囲(最大リーチ)の記載方法についてです。 下記の記事を書くために調べていた時に気が付きました。 fa-robot-watch.com 6自由度での動作範囲記載 6軸の垂直多関節ロボットの動作範囲を論じる場合、下記の不二越のロボット動作範囲…
今回は協働ロボットの手首構造についてです。 手首の関節について 通常の6軸多関節ロボットは、下記の図のような関節配置をしているものが多いです。 (当ブログのロボット構造の図示方法はこちらをご覧ください:本ブログでのロボット模式図について - FA…
少し前の話ですが(2022年6月)、Universal Robot社から20kg可搬の新型UR20が発売されました。 単なる大型化ということではなく、内部の設計を見直し再設計した機種ということで力が入っています。 外観も、今までの機種からモディファイされており、全体的…