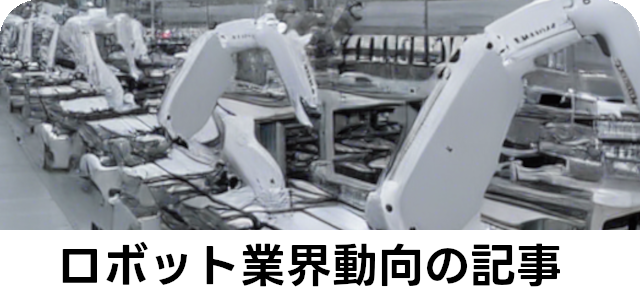2023-01-01から1年間の記事一覧
機械設計に限らず、設計のやりがいってなんだろうと考えたことがあると思います。 私の場合の、設計のやりがいについて書きたいと思います。 慣れからのマンネリ化 設計者になってすぐの頃は、とにかく色々な知識を吸収するのに必死で、あまり余計なことを考…
減速機の仕様などでよく目にするバックラッシ・ヒステリシス・ロストモーションを、産業用ロボット位置決め精度と関連付けて説明します。 精密減速機の位置決め精度について バックラッシ ヒステリシス ロストモーション ギヤ・ベルト・プーリなどの位置決め…
2023国際ロボット展を見学してきましたので、感想を残しておきたいと思います。 ※写真が少ないですがご了承ください。(写真は一言許可を得て撮影しています) 今年のトレンドは? EVバッテリの搬送 FANUCの新型1000kg可搬、500kg可搬ロボット Universal Rob…
2023国際ロボット展を見学して、一番印象に残ったMujinについてまとめました。 全体の感想は別でまとめたいと思います。 Mujinとは Mujinの製品はコントローラ 守備領域をどんどん広げている Mujinのハード開発は限定的 ロボットメーカの商売あがったりの可…
職場のルール、特に安全に関するルールの話です。 リスクアセスメント・リスク低減に関連する話として紹介いたします。 リスクアセスメントの最後はルール作り とある職場での事例(仮想) 労災対策でルール追加 新人が来たら そんなこんなでグダグダに ルー…
自動車好きな方であれば、この車種はこのメーカのOEMなどと聞いたことがあるかと思いますが、ロボット業界でのOEMはあるのか?どんな形態か?について解説していきます。 OEMとは メリットデメリット 提供側(A社)のメリット 提供側(A社)のデメリット 販…
垂直多関節ロボットの設置形態について紹介します。 はじめに 床置き設置(Floor mount) 天吊り設置(Ceiling mount) 壁掛け設置(Wall mount) 傾斜設置(Angled mount) 棚置き(Shelf mount) まとめ はじめに 産業用ロボットは地面に設置して使うだけ…
本記事はちょっとマニアックな小ネタです。 人とロボットが協働運転する際の要件事項のうちの「動力と力の制限」についてです。 「動力」と「力」という言葉が使い分けられている カギは2006年版にあり まとめのようなもの 「動力」と「力」という言葉が使い…
産業用ロボットのロボットアームを構成する機械要素についてまとめていきます。 本記事ではさらっと列挙していますので、より詳しくはリンク先記事や各メーカHPなどをご覧ください。 (イラスト)ロボット(6軸)|FA計画.comから画像使用 原動機 サーボモー…
機械安全についての記事をいくつか書いていますが、リスクアセスメント等についてまとめていなかったので、説明していきたいと思います。 すでにいろいろな会社ホームページ・ブログなどで解説がありますので、いまさらという気もしますが、個人的な意見や注…
協働ロボットを扱う場合も含めた機械安全について話をする際、安全やリスクという言葉がたびたび出てくるので、一度まとめておきます。 (この記事は短いです:860文字程度) 「リスク」とは 「安全」とは 「リスク」とは ISO12100での定義を引用します。 リ…
2023年6月27日付でABBが4モデル22バリエーションのロボットをリリースしました。 ニュースリリース:ABB、4つの省エネモデルと22のバリエーションで大型ロボットファミリーを拡充22機種も同時発売!?と、かなりのインパクトがありますね。 下記の動画内でモ…
ときおり、「80W以下のロボットなら安全柵は不要なんでしょう?」という声を聞くことがあります。また、「協働ロボット=モータ出力が80W以下のロボット」と思っている方もいるかもしれません。 いわゆる「80W規制」については、法律と通達が絡んで混乱しが…
会社の文化によって様々な意見があると思うのですが、1つの考え方として読んでいただければと思います。私はメカ屋ですが、下記のような制御に関する情報も発信しています。 fa-robot-watch.com その理由は、この記事のタイトル通り「製品の安全対策は機械設…
本記事は、制御(電気・ソフト)のことはあまり分からないという人*1が、大枠のイメージを掴むことを目的としています。設備に関して話をしていると、以下のようなワードが出てくると思います。 安全関連部 安全適合 カテゴリ3PLd ・・・ そのような用語が…
前記事の①は、長い前置きになってしまいました。 いよいよ本題の「安全適合の監視停止」について説明していきます。 fa-robot-watch.com 規格上は 世間の協働ロボットはカテゴリ2停止が多い 実際のシステムはどうなるか 単純な例 中間領域を設ける例 人とロ…
協働ロボットの要件の1つである「安全適合監視停止」について解説していきたいのですが、まずはロボットの「停止」について説明をしていきます。 主な出典は、ISO10218-1:2011(JIS B 8433-1:2015)、IEC60204-1:2016(JIS B 9960-1:2019)です。この辺は知って…
サイズが全然違うのに、似たような思想で設計されているロボットがあり、面白いと思ったので紹介します。 不二越(NACHI)のMC1000DL オリムベクスタ(オリエンタルモータ)のOVR480K5N、OVR680K5N、OVR880K5N 何が似ているか? 不二越(NACHI)のMC1000DL 1…
協働運転要求事項の1つである、「速度及び間隔の監視」*1について解説していきます。 なお、分かりやすさ優先で書いていきますので、詳細は規格を参照してください。 規格での記載 まずは間違った例から 正解はこちら 今後の展望 規格での記載 ISO10218-1(J…
今回は、ユニークな機構のロボットとして、スギノマシンのCRbをご紹介します。 www.sugino.com スギノマシンとは ロボットの構造 スコットラッセルリンクとは メリット まとめ スギノマシンとは スギノマシン HOME 株式会社スギノマシンは、富山県に本社のあ…
ロボットの配線で最も悩ましいのが、関節部分の処理です。 ロボット配線特有の難しさについて紹介していきたいと思います。ロボットの配線が特別に難しい!ということを言いたいわけではありません。 他分野での配線も、特有の難しさがあると思います。 こう…
前回の記事では、必須の配線(ロボット駆動用配線)とユーザ用配線で分けて考えてみましたが、中を通すか外を通すか、という見方もありますので紹介します。 中を通す メリット デメリット 外を通す メリット デメリット 防じん防滴(IP性能)について まと…
ロボットの配線・配管について紹介していきたいと思います。 (なお、制御装置内の配線や、制御装置とロボットの間の配線については除きます) 1回目はロボット内を通っている配線の分類です。 ロボットの配線は、必須の配線とオプショナルな配線に分けて考…
産業用ロボットは、ツールを付け替えることで様々な用途に使用できる汎用性が特徴ですが、悪く言えば器用貧乏とも言えます。 ですが、特定用途(ニッチ?)のために存在するロボットもあります。 それが、「自動車塗装工程でのドア開閉用ロボット」というピ…
協働ロボットのハンドガイドとダイレクトティーチの呼称について、整理してみたいと思います。 私は最初、ハンドガイドとダイレクトティーチは違うもの?と勘違いしていました。 先にまとめ 規格を確認 ハンドガイド ISO10218-1(JIS B 8433-1) TS15066(TS B …
ロボットにも得意な向き、不得意な向きがあるという話です。 「右利き、左利き」は本記事で勝手に呼んでいます。 左右対称のアプリケーション 手首が左右非対称 例1・不二越のSRA100H 例2:川崎重工のBX100N 第4軸をひっくり返せば? 左右に気をつけない…
以前、ロボットの機構として平行リンク機構を紹介しました。 fa-robot-watch.comその中で、平行リンク機構のロボットは、リンク構造ではないロボットに比べて動作範囲が狭くなると書きましたが、もう少し具体的に説明しようと思います。 なお、今回の記事で…
トヨタ自動車がギガプレス(ギガキャスト)に乗り出すというニュースがありました。*1 motor-fan.jpこれを機に自動車の製造方法が大きく変わるのではないか?と言われています。 自動車業界と二人三脚で発展したロボット業界にも、当然影響があると思います…
前回の記事はほぼ規格の説明になってしまいましたが、後半の今回は実際の測定について紹介していきます。 ①を未読の方は、まずはこちらからどうぞ。 fa-robot-watch.com 測定装置の概要 力センサー・圧力センサー ばね おもり スライド機構 その他 測定方法 …
協働運転のシステム構築で、ロボットの接触検知機能*1を活用する場合、リスクアセスメントの一環として接触した時の人体へのダメージを評価する必要があります。 「どんな手順でどんな項目を実施するのだろう?」「まさか実際に人がぶつかってみるわけにもい…