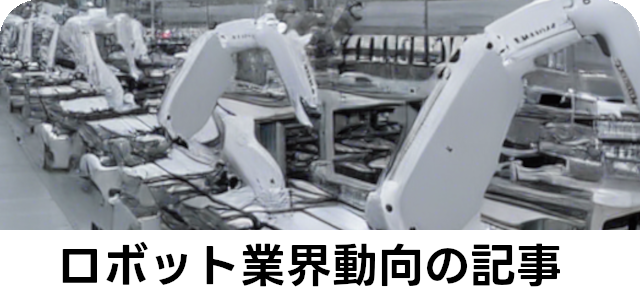本記事はちょっとマニアックな小ネタです。
人とロボットが協働運転する際の要件事項のうちの「動力と力の制限」についてです。
「動力」と「力」という言葉が使い分けられている
人とロボットが協働運転するための要求事項の1つに、人とロボットが衝突しても、人に致命的な危害を及ぼさないように対策するというものがあります。
ISO10218-1:2011の中の
5.10協働運転要求事項
5.10.5 本質的設計又は制御による動力及び力の制限
という項目で規定されています。
が、「動力及び力」と書いてあり、ん?と感じます。
また、協働運転のための要求事項を詳説したISO/TS 15066にも、
動力、力、並びに動力及び力を制限されたロボットシステム
といった文言があり、「動力」と「力」を意図的に使い分けていることが分かります。
(英語だとpowerとforceです)
「動力」と「力」?
それぞれ具体的に何を指すのか?と疑問に思われる方もいると思います。
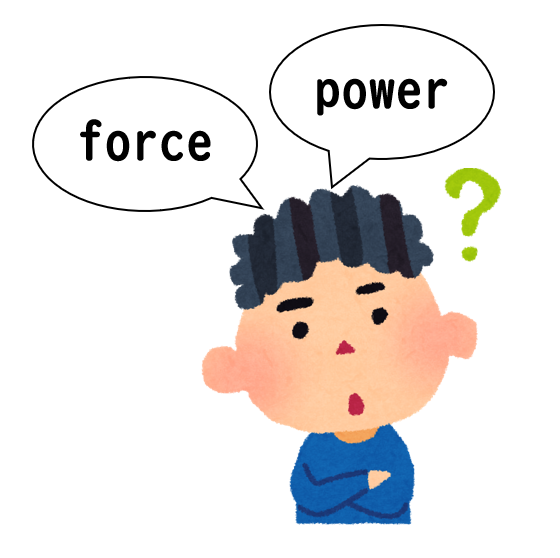
カギは2006年版にあり
私もしばらく疑問に思っていたのですが、その答えは、1つ前の版のISO10218-1:2006にありました。
5.10協働運転要求事項
5.10.5 本質的設計による動力及び力の制限
ロボットは、メカニカルインタフェース又はTCPにおいて最大動力80W, 又は最大静的力150N(リスクアセスメントに基づいていずれかを決める)を保証するように設計しなければならない。
この記載だと、「動力」はモータ出力(W数)であり、「力」は外部に与える力のことだな、とすんなり理解できます。
ですが、2011年に改版された際に、80Wや150Nという記載が無くなり、TS15066の記載内容も人体に与える力についての記述が主になっています。
にもかかわらず、「動力及び力」という文言はそのまま残っているため、分かりづらくなっているのだと思います。
余談ですが、2006版では80W以下のモータを使用しなければならないわけではなく、
5.10.6制御システムによる動力及び力の制限
制御機能を5.10.5における動力と力との最大値を超えないように利用する場合は、(後略)
という記載もあるため、200Wのモータを使用した上で最大電流を制限するなど、80W相当以下に出力を制限していれば規格に合致します。
まとめのようなもの
繰り返しになりますが、ISO10218からは80Wの記載が無くなり、TS15066も人体へ与える力(および圧力)を主眼としています。
現実的にも、動力(W数)を制限したとしても、衝突した際のロボットの姿勢などにより人体への力は大きく異なってしまうため*1、最終的なリスク評価は、人体に与える「力」がどうかを考えていればいいでしょう。
※もちろん、小さなモータを使った方が力も小さいので、可能な限り小さいモータを選定することも重要です。
今後の改版で「力の制限」というすっきりした表現になることを期待しています。
なお、衝突時にロボットが人体へ与える力の評価については過去記事でまとめております。
fa-robot-watch.com
fa-robot-watch.com
*1:さらには、バランサーなどを駆使すればモータのW数を抑えて大きい力を出すことは可能です