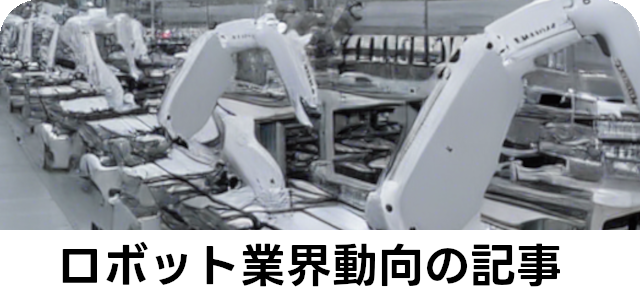ときおり、「80W以下のロボットなら安全柵は不要なんでしょう?」という声を聞くことがあります。また、「協働ロボット=モータ出力が80W以下のロボット」と思っている方もいるかもしれません。
いわゆる「80W規制」については、法律と通達が絡んで混乱しがちなので、整理しつつ説明していきたいと思います。
前半で大枠を説明し、後半で細かい法規の引用などを記載します。
なお、本記事の内容は日本国内に限定されます。
モータ出力が80W以下の場合、産業用ロボットではない
労働安全に関する法律上、「産業用ロボット」を扱う際は特別教育が必要であったり、安全柵の設置*1が必要といった制約があります。
ですが、モータ出力が80W以下の場合、産業用ロボットとはみなされません。
これは各関節の内、最大の出力を持つもので判断します。
例えば、80W・60W・40W・40W・20W・10Wというような組み合わせの6軸ロボットならば、産業用ロボットとはみなされません。*2
(これ以降は、簡単に出力80W以下のロボットと書きます)
逆の言い方をすれば、出力が80Wより大きいロボットは法律で規制されていると言えます。
これが「80W規制」と呼ばれているのです。*3


協働ロボットを柵無しで使っていい根拠は?
ちょっとまてよ?と思う方もいるでしょう。協働ロボットでは80Wよりも大きいモータが使われている場合も多いからです。
この場合の法的根拠は、2013年に厚生労働省から出された通達です。
正式には平成25年12月24日 基発1224第2号で、2号通達と略されることもあるので、これ以降はそのように呼びます。
この2号通達で「リスクアセスメントをしたら、安全柵無しでロボットを運転してもよい or ISO10218-1,2に基づいた設計・運用を、安全柵の代替としてよい」と定められました。
これにより安全柵無しでのロボット運用に法的根拠が与えられたわけです。*4
参考資料:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/pamphlet_140115.pdf

時系列で
さて、現状だけを見ると、結構すっきりしているように感じます。
混乱の原因を探るために、時系列でみていきます。
国内の法律・通達に加えて、ISOやその他の事項も記載しています。
| 1983年 | 出力80W以下のロボットは、産業用ロボットとはみなさないとする労働省告示 |
|---|---|
| 1992年 | ISO10218:1992 発行 |
| 2006年 | ISO10218-1:2006 発行:協働運転の要求事項が追加. 80Wへの言及あり |
| 2007年 | JIS B8433-1:2007発行(ISO10218-1:2006を反映) |
| 2008年 | ユニバーサルロボット販売開始 |
| 2011年 | ISO10218-1:2011 発行:80Wへの言及削除 |
| 2013年 | 2号通達により、安全柵無しでロボットを運用してもよい条件が示される |
| 2015年 | JIS B8433-1:2015発行(ISO10218-1:2011を反映) |
| 2016年 | ISO T/S 15066発行 |
1983年の告示により「出力80Wを超えるものは産業用ロボットとして規制=安全教育・安全柵必須」となりました*5。
告示が出てしばらくは、ロボットは重筋作業のための大型のものが多かったため、そのような認識でそれほど問題にはならなかったのだと思います。
ですが、協働運転の要求事項が追加されたISO10218-1:2006が発行、2008年にユニバーサルロボット販売開始など、協働ロボットというものが出現して話が変わってきます。
ISO10218-1:2006はJIS B8433-1:2007となりましたが、法律への引用はなく、協働ロボットをどう扱えばいいか国内の法的根拠がふわっとしていたのです。*6*7
特に、2011年にISO10218-1:2011に改定された際に80Wへの言及もなくなり、さらに方向性に混乱が生じます。*8
2013年の2号通達により、ようやくメーカやシステム提供側の責任・方針が明確になり、協働ロボットの普及・安全柵なしでの運用が後押しされることになりました。
(このことを指して、「80W規制の緩和」と呼ぶことがあります)
上記のような若干の混乱の期間があったことが尾を引き、80W規制と協働ロボットについてごっちゃになってしまっている人がいるのだと思います。
まとめ
このように時系列でみると、過渡的な状況があったために混乱が生じたことを理解していただけると思います。
ですが、今は最新の国際規格と国内法規(通達)がリンクしている状態のため、ISO10218-1, 2やTS15066を基本としていく姿勢でいいと思います。*9
(私見)80W規制は気にしなくてよい
なお、私の意見としては、80W規制はあまり意識しなくてもいいと思います。
理由を以下に書きます。
出力80W以下だろうと危険は生じる
いかに出力80W以下で産業用ロボットのくくりから外れると言っても、リスクアセスメントはすべきですし、減速比や機構などで大きな力が出ることもあります。産業用ロボットのカテゴリから外れていても、FAで使う場合産業用設備の一部であることに違いはありません。
変に「80W以下だから安全」と先入観を持たない方がいいでしょう。
80W規制は日本国内だけの話
一時はISO10218-1にも80Wについて言及されていましたが、2006⇒2011の改定で削除されました。
現在は、80W規制は日本国内だけで通用する話になっており、将来的に、国際的な運用に合わせる形で上記の通達が取り消される可能性もあります。
これ以降は法規・通達の引用や出典の記載となります
法規の引用・出典など
基本的には和暦で記載されています。西暦は私が追加しました。
また、強調表示も私が追加しました。
労働安全衛生規則
労働安全衛生規則第一編 通則
第四章 安全衛生教育
(特別教育を必要とする業務)
第三十六条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
(中略)
三十一 マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。以下この号において同じ。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く。以下「産業用ロボツト」という。)の可動範囲(記憶装置の情報に基づきマニプレータその他の産業用ロボツトの各部の動くことができる最大の範囲をいう。以下同じ。)内において当該産業用ロボツトについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認(以下「教示等」という。)(産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000032より引用
「その他厚生労働大臣が定めるものを除く」という文言がミソです。
第二編 安全基準
第一章 機械による危険の防止
第九節 産業用ロボツト
(運転中の危険の防止)
第百五十条の四 事業者は、産業用ロボツトを運転する場合(教示等のために産業用ロボツトを運転する場合及び産業用ロボツトの運転中に次条に規定する作業を行わなければならない場合において産業用ロボツトを運転するときを除く。)において、当該産業用ロボツトに接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、さく又は囲いを設ける等当該危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。
この一文は結構目にした方も多いかと思います。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000032より引用
※労働安全衛生規則は最新のものを参照しています。
昭和五十八年(1983年)労働省告示第五十一号(労働安全衛生規則第三十六条第三十一号の規定に基づく厚生労働大臣が定める機械)
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十六条第三十一号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める機械を次のように定め、昭和五十八年七月一日から適用する。
労働安全衛生規則第三十六条第三十一号の厚生労働大臣が定める機械は、次のとおりとする。
一 定格出力(駆動用原動機を二以上有するものにあつては、それぞれの定格出力のうち最大のもの)が八〇ワツト以下の駆動用原動機を有する機械
二 固定シーケンス制御装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、上下移動、左右移動又は旋回の動作のうちいずれか一つの動作の単調な繰り返しを行う機械
三 前二号に掲げる機械のほか、当該機械の構造、性能等からみて当該機械に接触することによる労働者の危険が生ずるおそれがないと厚生労働省労働基準局長が認めた機械
・労働安全衛生規則第三十六条第三十一号の規定に基づく厚生労働大臣が定める機械(◆昭和58年06月25日労働省告示第51号) より
労働安全衛生規則内の「その他厚生労働大臣が定めるものを除く」という文言プラス、この告示を根拠として、出力80W以下のロボットが産業用ロボットから除外されます。
平成25年(2013年)12月24日 基発1224第2号
5 第150条の4関係
(中略)
(2)産業用ロボットを使用する事業者が、労働安全衛生法第28条の2による危険性等の調査(以下「リスクアセスメント」という。)に基づく措置を実施し、産業用ロボットに接触することにより労働者に危険の生ずるおそれが無くなったと評価できるときは、本条の「労働者に危険が生ずるおそれのあるとき」に該当しないものとすること。
(中略)
(3) 「さく又は囲いを設ける等」の「等」には、次の措置が含まれること。
(中略)
ホ 国際標準化機構(ISO)による産業用ロボットの規格(ISO 10218-1:2011及びISO10218-2:2011)によりそれぞれ設計、製造及び設置された産業用ロボット(産業用ロボットの設計者、製造者及び設置者がそれぞれ別紙に定める技術ファイル及び適合宣言書を作成しているものに限る。)を、その使用条件に基づき適切に使用すること。なお、ここでいう「設置者」とは、事業者(ユーザー)、設置業者、製造者(メーカー)などの者のうち、設置の安全条件に責任を持つ者が該当すること。
https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/var/rev0/0108/4335/20131226163424.pdfより引用
補足的に下記も参考にしました。
- 改定内容の説明:・産業用ロボットに係る労働安全衛生規則第150条の4の施行通達の一部改正について(◆平成25年12月24日基発第1224002号)
- 解説パンフレット:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/pamphlet_140115.pdf
- 差分(中央労働災害防止協会公開の資料):https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-54/hor1-54-62-1-2.pdf
この通達により、
- 適切なリスクアセスメントにより労働者に危険が生ずる恐れがなくなったとすることができる
- ISO10218-1および2に基づいた設計・使用が安全柵の設置と同様の保護方策とみなせる
といったことの根拠ができました。
ISO10218-1
2006
5.10.5 本質的設計による動力及び力の制限
ロボットは、メカニカルインタフェース又はTCPにおいて最大動力80W、または最大静的力150N(中略)を保証するように設計しなければならない。
2011
5.10.5 本質的設計又は制御による動力及び力の制限
ロボットの動力又は力を制限する機能は5.4に従わなければならない。
※5.4は安全関連制御システム性能(ハードウェア及びソフトウェア)
この改定により、80Wという文言が削除されました。
なお、日本の法律では、出力80W以下のロボットは産業用ロボットのくくりから外れていますが、ISO10218-1:2006では出力80W以下でも産業用ロボットのくくりであり、安全を担保するための手法の1つとして出力80W以下にする、という考え方の違いがあります。
*1:安全柵以外の代案も示されていますが、ここでは簡単に安全柵とします
*2:あくまで「労働安全に関する法律の上では」です
*3:文面としては出力80W以下が例外的に除外されているのですが、「80W規制」が指すものは出力80Wより大きいロボットであり、少しややこしいと感じます
*4:強制力も発生したわけですが
*5:厳密には異なるのですが、そのような共通認識ができ、安全が担保されていたことは間違いないと思います
*6:ロボットメーカーやSIerが、独自にその時点での法律や通達、JIS, ISOの内容を組み合わせて協働ロボットを運用することも不可能ではなかったと思いますがどうしても説得力に欠けます
*7:現時点でも、JIS B8433-1,2ともに法律から引用されてはいないという認識です。間違っていたらご連絡ください。一応こちらでチェックしました:日本産業標準調査会:データベース-強制法規情報
*8:なお、ISO10218-1:2006に80Wの言及がされていたことと、日本の80W規制に関連があったかどうかは、調べても分かりませんでした・・・
*9:次回のISO改定時、若干のタイムラグが生じるでしょうが、基本はISOにキャッチアップする動きだと思います