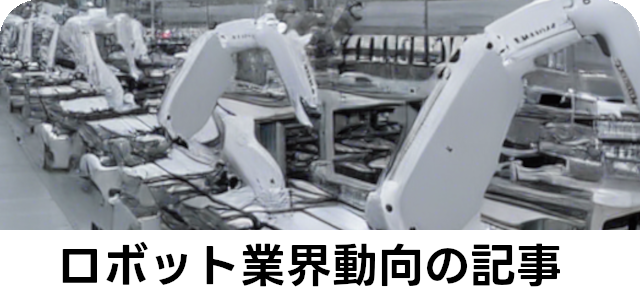2023年6月27日付でABBが4モデル22バリエーションのロボットをリリースしました。
ニュースリリース:ABB、4つの省エネモデルと22のバリエーションで大型ロボットファミリーを拡充
22機種も同時発売!?と、かなりのインパクトがありますね。
下記の動画内でモジュラー設計を活用したと言及がありますが、どういうことか公開情報をもとに解説(推測)していきたいと思います。
ABBの公式サイトでスペック一覧が公開されているので、それを元にして考えていきます。*1
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108468A2787&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
機種一覧
- IRB6710-210/2.65
- IRB6710-200/2.95
- IRB6710-175/2.65LID
- IRB6710-175/2.95LID
- IRB6720-240/2.65
- IRB6720-210/2.8
- IRB6720-170/3.1
- IRB6720-215/2.5LID
- IRB6720-215/2.65LID
- IRB6720-200/2.8LID
- IRB6720-150/3.1LID
- IRB6730-270/2.7
- IRB6730-240/2.9
- IRB6730-210/3.1
- IRB6730-220/2.9LID
- IRB6730-190/3.1LID
- IRB6740-310/2.8
- IRB6740-260/3.0
- IRB6740-240/3.2
- IRB6740-270/2.8LID
- IRB6740-230/3.0LID
- IRB6740-220/3.2LID
列挙するだけでもかなりスペースを取りますね。
ネーミングについてですが、末尾の「XXX/X.XX」が「可搬重量/リーチ」という法則になっているようです。
例えば、IRB_6710-210/2.65であれば、210kg可搬、2.65mのリーチという具合です。
リーチについては、動作範囲図と多少数字が異なる(数十mm程度)のですが、機種名の数字で話をしていきます。
上側アーム・下側アームの長さ違い
まずは、末尾にLIDが付いていない機種について見ていきます。
- IRB6710-210/2.65
- IRB6710-200/2.95
- IRB6720-240/2.65
- IRB6720-210/2.8
- IRB6720-170/3.1
- IRB6730-270/2.7
- IRB6730-240/2.9
- IRB6730-210/3.1
- IRB6740-310/2.8
- IRB6740-260/3.0
- IRB6740-240/3.2
模式図で説明しますが、

外観から推測するに、
「第1軸部分」「第3、4軸部分」「第5、6軸部分」は全機種同じ、「第2軸部分」が2種類、「下アーム」が3種類、「上アーム」が3種類というようになっているようです。*2
主に、上アームと下アームの長さの組合せでバリエーションを出しているようです。
可搬重量とリーチで、シリーズごとにプロットしてみると、下記のように右下がりのグラフになります。

駆動系は共通*3で、リーチが長くなるほど可搬重量を下げている、と推測できます。
この手法で、4つの基本設計(シリーズ)を11ケのバリエーションに増やしています。
ベース機種+手先延長フランジ
先ほど末尾にLIDと付いているものを除外しました。
LID付きの機種は、ツール取り付け面に延長フランジが装備されているタイプのようです。
仕様書の側面図をじーっと眺めるとベース機から派生していると推測できます。
各シリーズごとに見ていきます。
IRB6710
- IRB6710-210/2.65⇒75/2.65LID(可搬重量210kg⇒175kg、リーチは2.65m)
- IRB6710-200/2.95⇒175/2.95LID(可搬重量200kg⇒175kg、リーチは2.95m)
横軸にリーチ・縦軸に可搬重量をとり、LIDの有無別でプロットすると、下記のようになります。

IRB6720
- IRB6720-240/2.65⇒215/2.65LID(可搬重量240kg⇒215kg、リーチは2.65m)
- IRB6720-210/2.8⇒200/2.8LID(可搬重量210kg⇒200kg、リーチは2.8m)
- IRB6720-170/3.1⇒150/3.1LID(可搬重量170kg⇒250kg、リーチは3.1m)
(IRB6720-215/2.5LIDのベース機種だけ見当たりませんでした)

IRB6730
- IRB6730-240/2.9⇒220/2.9LID(可搬重量240kg⇒220kg、リーチは2.9m)
- IRB6730-210/3.1⇒190/3.1LID(可搬重量210kg⇒190kg、リーチは3.1m)

IRB6740
- IRB6740-310/2.8⇒270/2.8LID(可搬重量310kg⇒270kg、リーチは2.8m)
- IRB6740-260/3.0⇒230/3.0LID(可搬重量260kg⇒230kg、リーチは3.0m)
- IRB6740-240/3.2⇒220/3.2LID(可搬重量240kg⇒220kg、リーチは3.2m)

このように、ツール取り付け部が延長された分、可搬重量的には不利になっており可搬重量が少なくなっています。
22機種の内10機種は、ベース機種+手先延長フランジという形の派生設計と言えます。
ベース機種が見当たらないと書いたIRB6720-215/2.5LIDについては、LID付きの機種のみが設計されたと考えられます。おそらくは商業的な理由でしょう。
モジュラー設計
下アーム・上アームの長さの組合せと、ツール取り付け部の延長で4つの基本設計を22のバリエーションにまで増やしていることが分かります。
このような設計手法のメリットとしては、設計工数の削減や、部品共通化による調達面でのメリットが考えられます。
逆に、デメリットとしては、過剰スペック・過剰強度となる場合があります。
各コンポーネントは、基本的には最も大きな可搬重量の機種に合わせる必要がありますので、逆に可搬重量の小さな機種にとっては過剰スペックになります。
これらのメリット・デメリットは、ある程度調整が可能です。
例として、あるコンポーネントを共通化しつつ、4機種を設計する場合を考えます。

図の上段のように、4機種全てで共通化する場合、最も可搬重量の大きな機種Dに合わせる必要があります。
ですが、機種Aにとっては過剰なスペックとなります。
図の下段のように、2機種ずつで共通化する場合は、機種Bに合わせてAとBで共通化、機種Dに合わせてCとDで共通化となります。
過剰スペック度合いは軽減されますが、設計工数は増えます。
この辺のバランスをどうするかは、販売予定台数なども考慮しながら決定されているはずです。
まとめ
いかがだったでしょうか。
モジュラー設計については、基本的な事柄しか書けなかったので物足りない方もいるとは思いますが*4、ABBと言えば大企業で、垂直多関節・パラレルリンクロボット・SCARA・走行台車までラインナップに持っていますが、設計のマンパワーによるごり押しだけでなく、共通化設計を活用して設計工数をやりくりしていることが垣間見えて興味深いと思います。